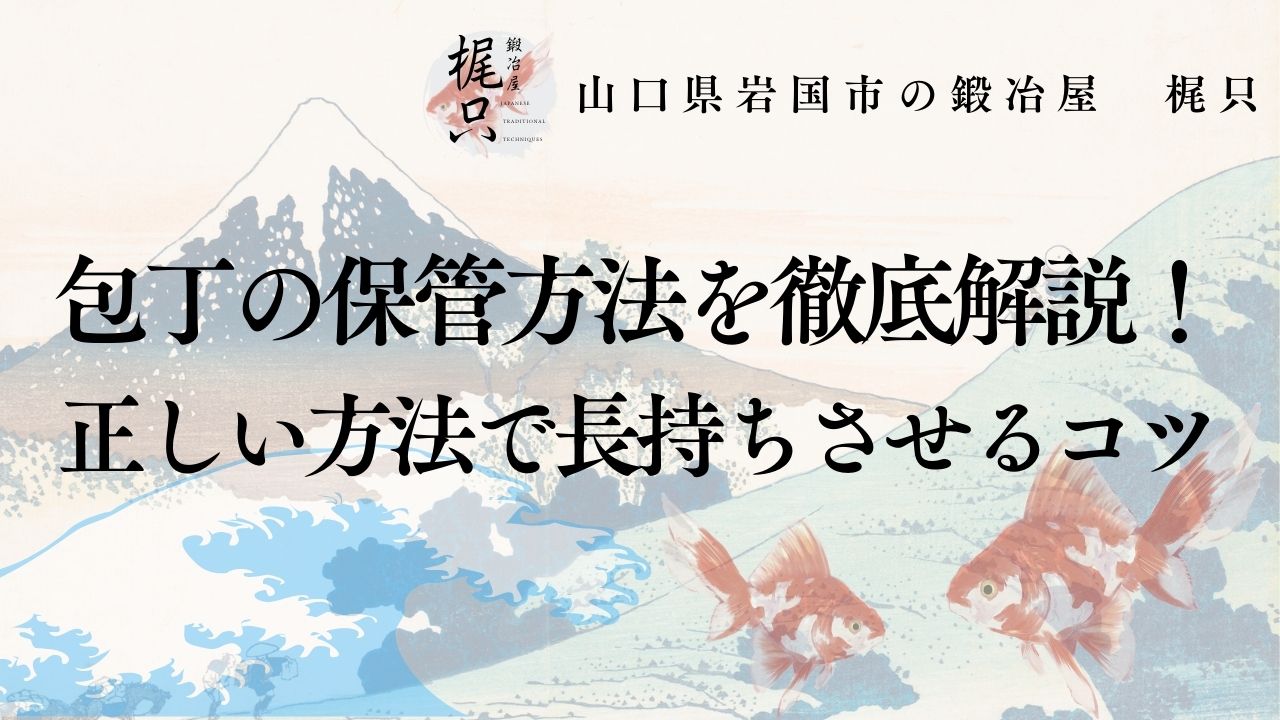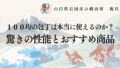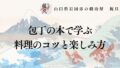包丁は料理に欠かせない道具ですが、その保管方法については意外と知らない人も多いのではないでしょうか?包丁の保管方法は、切れ味や耐久性、衛生面にも大きく影響します。間違った保管方法をしていると、包丁が錆びたり、傷んだり、菌が繁殖したりする可能性があります。そうならないためには、どのように保管すれば良いのでしょうか?
この記事では、包丁の保管方法について、以下の3つのポイントに分けて徹底解説します。
- 包丁の種類による保管方法の違い
- 包丁の保管場所の選び方
- 包丁の保管時の注意点
これらのポイントを押さえて、正しい方法で包丁を保管して、長持ちさせましょう!
包丁の種類による保管方法の違い
まず、包丁の保管方法は、包丁の種類によって異なります。包丁の種類は、主に以下の3つに分けられます。
- ステンレス鋼製の包丁
- 炭素鋼製の包丁
- セラミック製の包丁
それぞれの特徴と保管方法について見ていきましょう。
ステンレス鋼製の包丁
ステンレス鋼製の包丁は、最も一般的な包丁の種類です。ステンレス鋼は、鉄にクロムやニッケルなどを添加した合金で、錆びにくく、耐食性が高いのが特徴です。そのため、ステンレス鋼製の包丁は、水分や空気にさらされても、比較的安心して保管できます。ただし、完全に錆びないというわけではありません。長期間放置したり、酸や塩分に触れたままにしたりすると、錆びる可能性があります。また、切れ味は炭素鋼製の包丁に劣ります。
ステンレス鋼製の包丁の保管方法は、以下のようにします。
- 使用後は、水や中性洗剤で洗って、乾いた布で拭いてから保管する。
- 保管場所は、湿気の少ないところにする。
- 他の金属と接触しないようにする。
炭素鋼製の包丁
炭素鋼製の包丁は、鉄に炭素を添加した合金で作られた包丁です。炭素鋼は、硬くて切れ味が良いのが特徴です。そのため、炭素鋼製の包丁は、プロの料理人や料理好きの人に人気があります。しかし、炭素鋼は、錆びやすく、変色しやすいのが欠点です。水分や空気に触れると、すぐに錆びたり、黒ずんだりします。また、酸や塩分にも弱く、味や色が移ってしまうこともあります。
炭素鋼製の包丁の保管方法は、以下のようにします。
- 使用後は、水で洗って、乾いた布で拭いてから保管する。
- 保管場所は、湿気の少ないところにする。
- 他の金属と接触しないようにする。
- 錆びや変色を防ぐために、定期的に油を塗る。
セラミック製の包丁
セラミック製の包丁は、ジルコニアという素材で作られた包丁です。セラミックは、軽くて硬く、切れ味が長持ちするのが特徴です。そのため、セラミック製の包丁は、切りやすく、手に負担がかからないというメリットがあります。また、錆びないし、変色しないし、味や色も移りません。しかし、セラミックは、衝撃に弱く、欠けやすいのが欠点です。硬いものや骨などを切ったり、落としたりすると、簡単に割れてしまいます。また、切れ味が落ちたときには、自分で研ぐことができません。
セラミック製の包丁の保管方法は、以下のようにします。
- 使用後は、水や中性洗剤で洗って、乾いた布で拭いてから保管する。
- 保管場所は、衝撃を受けないところにする。
- 他の金属やセラミックと接触しないようにする。
- 専用のケースやシースに入れて保管する。
包丁の保管場所の選び方

次に、包丁の保管場所の選び方について見ていきましょう。包丁の保管場所は、以下の4つの種類があります。
- 引き出し
- 包丁立て
- マグネットバー
- 壁掛け
それぞれのメリットとデメリットについて見ていきましょう。
引き出し
引き出しは、最も一般的な包丁の保管場所です。引き出しには、以下のようなメリットがあります。
- 包丁が見えないので、見た目がすっきりする。
- 包丁が埃や汚れにさらされないので、衛生的に保管できる。
- 包丁が子供の手に触れないので、安全に保管できる。
しかし、引き出しには、以下のようなデメリットもあります。
- 引き出しの中で包丁が動いたり、ぶつかったりすると、傷ついたり、切れ味が落ちたりする。
- 引き出しの中が湿気ると、包丁が錆びたり、カビたりする。
- 引き出しの中で包丁を探すときに、手を切ったりする危険がある。
引き出しに包丁を保管する場合は、以下のように注意しましょう。
- 包丁は、専用のケースやシースに入れて
- 引き出しの中で固定する。
- 引き出しの中は、乾燥剤や防湿剤を入れて、湿気を防ぐ。
- 引き出しの中で包丁を探すときには、手袋を着用するか、注意深く行う。
包丁立て
包丁立ては、包丁を立てて保管する器具です。包丁立てには、以下のようなメリットがあります。
- 包丁が見えるので、使いたい包丁をすぐに取り出せる。
- 包丁が空気に触れるので、乾燥しやすい。
- 包丁が他のものと接触しないので、傷つきにくい。
しかし、包丁立てには、以下のようなデメリットもあります。
- 包丁が見えるので、見た目がごちゃごちゃする。
- 包丁が埃や汚れにさらされるので、衛生的に保管できない。
- 包丁が子供の手に触れるので、安全に保管できない。
包丁立てに包丁を保管する場合は、以下のように注意しましょう。
- 包丁は、刃先を下にして、包丁立てに立てる。
- 包丁立ては、水はねや油はねの少ないところに置く。
- 包丁立ては、定期的に洗って、清潔に保つ。
マグネットバー
マグネットバーは、包丁を磁力で吸着して保管する器具です。マグネットバーには、以下のようなメリットがあります。
- 包丁が見えるので、使いたい包丁をすぐに取り出せる。
- 包丁が空気に触れるので、乾燥しやすい。
- 包丁が他のものと接触しないので、傷つきにくい。
- 包丁が立てられない形状のものでも、保管できる。
しかし、マグネットバーには、以下のようなデメリットもあります。
- 包丁が見えるので、見た目がごちゃごちゃする。
- 包丁が埃や汚れにさらされるので、衛生的に保管できない。
- 包丁が子供の手に触れるので、安全に保管できない。
- 包丁が磁力によって磁化されると、切れ味が落ちる。
マグネットバーに包丁を保管する場合は、以下のように注意しましょう。
- 包丁は、刃先を上にして、マグネットバーに吸着させる。
- マグネットバーは、水はねや油はねの少ないところに置く。
- マグネットバーは、定期的に拭いて、清潔に保つ。
- 包丁は、定期的に研いで、磁化を防ぐ。
壁掛け
壁掛けは、包丁を壁にかけて保管する方法です。壁掛けには、以下のようなメリットがあります。
- 包丁が見えるので、使いたい包丁をすぐに取り出せる。
- 包丁が空気に触れるので、乾燥しやすい。
- 包丁が他のものと接触しないので、傷つきにくい。
- 包丁が立てられない形状のものでも、保管できる。
- 包丁が壁にかかるので、スペースを節約できる。
しかし、壁掛けには、以下のようなデメリットもあります。
- 包丁が見えるので、見た目がごちゃごちゃする。
- 包丁が埃や汚れにさらされるので、衛生的に保管できない。
- 包丁が子供の手に触れるので、安全に保管できない。
壁掛けに包丁を保管する場合は、以下のように注意しましょう。
- 包丁は、刃先を下にして、壁にかける。
- 壁掛けは、水はねや油はねの少ないところに置く。
- 壁掛けは、定期的に拭いて、清潔に保つ。
包丁の保管時の注意点
最後に、包丁の保管時の注意点について見ていきましょう。包丁の保管時には、以下のようなことに気をつけましょう。
- 包丁は、使用後に必ず洗って、乾いた布で拭いてから保管する。水分や汚れが残っていると、錆びやカビの原因になります。
- 包丁は、切れ味が落ちないように、定期的に研ぐ。研ぐときには、包丁の種類や素材に合った砥石やシャープナーを使う。
- 包丁は、保管場所によっては、子供やペットの手に触れないようにする。安全のために、鍵付きの引き出しや高いところに置くなどの対策をとる。
- 包丁は、保管場所によっては、火や熱に近づけないようにする。火や熱にさらされると、包丁の素材が変質したり、変形したりする可能性があります。
まとめ

以上が、包丁の保管方法についての解説でした。包丁の保管方法は、包丁の種類や素材によって異なりますが、共通して言えることは、以下の3つです。
- 包丁は、使用後に洗って乾かしてから保管する。
- 包丁は、他のものと接触しないように保管する。
- 包丁は、湿気や衝撃から遠ざけて保管する。
これらのポイントを守って、正しい方法で包丁を保管して、長持ちさせましょう!